令和5年度交付事業取材レポート
取材レポートでは、各務原市まちづくり活動助成金 令和5年度交付事業の活動の様子を紹介しています。(レポートの内容は、事務局の取材や団体からのヒアリングなどをもとに作成します。)
令和5年度各務原市まちづくり活動助成金 取材レポートNO.5
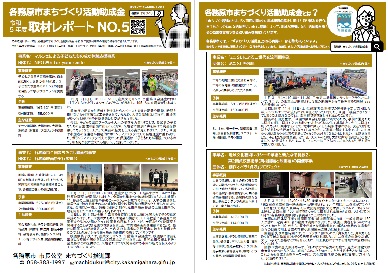
マルシェによる子どもの成功体験応援事業(NPO法人 for your smile)

12月2日(土曜日)午後3時~5時、産業文化センター2階第3会議室において、「子どもものづくりマルシェプログラム」の前日準備が行われました。参加者は各ブースを飾ると同時に、会場の展示も協力して行い、風船やクリスマスカラーが目を引く魅力的な会場になりました。開催当日は他の参加者のブースを楽しむ余裕がないことから、子どもたちのブースの準備が整ったところで時間が設けられ、参加者が互いのブースを見て回りました。
12月3日(日曜日)のマルシェ当日は、理事長の松原英人さんのあいさつから始まり、子ども33人と大人2人がブースを構えました。
会場には、一般来場者495人が訪れました。開場10分で一般来場者が100人を超え、その後も出店者の親族や友人などを中心にさまざまな年代の方がコンスタントに訪れましたが、前年度の反省から混雑を避けるためスペースを考えた配置や動線、時間を掛けない受付方法など工夫をされていたため、大きな混雑には至らず、来場者がゆっくりと買い物や体験を楽しむ姿が見られました。
今回、子どもの出店ブースから大人の姿を極力無くすことで、参加者の子どもたちの自主性が前面に出ることとなり、来場者に個別に声を掛けて商品を体験してもらうなど、工夫して商品の魅力を伝える姿が見られました。また、前年度は受付を団体スタッフや他団体に頼る状況でしたが、今回は参加者の保護者が積極的にボランティアスタッフとして会場運営に携わりました。ボランティアスタッフとして携わった保護者は、「子どもたちが頑張っているので、私も何か役に立てたら嬉しい。」と話していました。
会場には、活動の経緯がわかるグラフィックレコーディングの展示や、来場者がコメントを付箋に貼って残せるボードを用意。募金箱も設けられ、募金をした方にはお礼の品が用意されていました。活動に共感した来場者は、「少しだけど、支援になれば。」と募金をしたり、応援メッセージを書くなどして活動を応援していました。
各務原市全国まちおこし映画祭事業(各務原映画祭実行委員会)

1月7日(日曜日)正午~午後6時30分、産業文化センター1階あすかホールにて「各務原映画祭」が開催されました。全国から集まった地域映画(まちおこし映画)11作品の上映と監督や俳優のトークショーが無料で行われ、大勢の来場者は普段あまり触れる機会のない地域映画や映画製作の裏話などを楽しみました。また、会場ロビーでは、過去に団体が制作した市内映画作品の上映と市内ロケ地を紹介したパネルの展示も行われました。
第1部から第4部まで長時間に渡る上映にも関わらず多くの観客が詰めかけ、第4部の「ロイヤル劇場の夢」では満席となりました。代表の大野さんは閉会の挨拶で、10年程前に各務原で映画祭をやりたいと思いたって映画製作団体を立ち上げ、今回ようやく映画祭を開催することができた喜びを話されました。市内で映画祭を開催することで、新たな関係人口が増えることと、市内外の来場者に各務原市の魅力を発信できるのではとの思いから今後も映画祭を市内で続けていくそうです。
映画祭終了後には、産業文化センター2階第3会議室で、映画祭に作品を出展した監督や関係者による交流会が行われました。各務原市の郷土料理・金魚飯などの提供など、来場者だけでなく関係者にも市内の魅力を伝えるよう工夫されていました。「ロイヤル劇場の夢」に出演した岐阜県出身の女優・桜木梨奈さんは「自分の住むまちのよさを再発見し、郷土愛が集まるような場をつくっていけたら」と話されました。
ミニSLによる三世代交流再開事業(ミニSL各務原)

1月31日(水曜日)午前10時~11時30分、子苑第二幼稚園のサッカーグラウンドにおいて、ミニSLの乗車会が開催され、3歳の未満児から年長児までの園児322人が乗車しました。
当初は11月11日(土曜日)に保護者会主催での開催を予定していましたが、インフルエンザの流行により中止となっていました。今回、「機会がなくなってしまうのは残念なので」と、園主催で場を設けられたとのことです。
園長の石田先生は、「今回の乗車会を学習とつなげるため、事前に園児たちに切符を渡し、切符を入れるポシェットをつくるなどして準備した。先生に切符を切ってもらい、乗車することで、電車に乗ることの疑似体験になる。現在では『切符を切る』という行為がなくなってしまったが、ご家庭で話をする中で、おじいちゃんやおばあちゃんに昔の話をしてもらうきっかけになるかもしれない。」と話されました。
子どもたちが乗車後、ミニSLメンバーに対し大きな声で「ありがとうございました。」と挨拶をすると、ミニSLメンバーは子どもたちに「またね」と、手を振って応えていました。
地域文化芸術レガシーの承継と新たなる挑戦2:第2回貞奴芸術祭(萬松園編と映画編)の開催事業(創作オペラ「貞奴」プロジェクト)

3月3日(日曜日) 午後1時~4時30分産業文化センターあすかホールにおいて、「第2回貞奴芸術祭~映画編~」が開催され、90年前に川上貞奴がプライベート映像として残した貞照寺入仏式記録映画(文化財課デジタルアーカイブ)の上映と、貞奴生誕150周年をきっかけに撮影された映画「貞奴、大いに笑う」が上映されました。
会場には団体関係者や映画関係者・報道関係者に加えて一般来場者450人が訪れ、定員486名の座席は満席になりました。映画出演者をきっかけにイベントを知った10代から、歴史が好きな高齢者まで、幅広い年代の来場者が各々の目線で川上貞奴の存在や地域映画の魅力に触れました。
開催前後や休憩時間には、21プラザに設けられた「貞奴さんと、貞奴さんをめぐる市民活動展」にも多くの来場者が訪れました。
活動展では、創作オペラ「貞奴」プロジェクトや各務原映画祭実行委員会だけでなく、各務原市教育委員会・中山道鵜沼宿ボランティアガイドの会・名古屋市旧川上貞奴邸「文化のみち二葉館」・茅ヶ崎の「音貞オッペケ祭」・市内和菓子店の「河田秀正堂」が展示に協力。川上貞奴の生涯や活躍、文化へ与えた影響などの紹介とともに、川上貞奴にまつわる地域での活動が紹介されました。
開催前後や休憩時間には、21プラザに設けられた「貞奴さんと、貞奴さんをめぐる市民活動展」にも多くの来場者が訪れました。活動展では、創作オペラ「貞奴」プロジェクトや各務原映画祭実行委員会だけでなく、各務原市教育委員会・中山道鵜沼宿ボランティアガイドの会・名古屋市旧川上貞奴邸「文化のみち二葉館」・茅ヶ崎の「音貞オッペケ祭」・市内和菓子店の「河田秀正堂」が展示に協力。川上貞奴の生涯や活躍、文化へ与えた影響などの紹介とともに、川上貞奴にまつわる地域での活動が紹介されました。
団体代表の金光順子さんは、「さまざまな方の協力のお陰で、過去の活動では出会えなかった方たちにも貞奴さんのことを知っていただける機会となりました。これからも貞奴さんをキーワードに、文化芸術活動の振興に貢献していけたら。」と話されました。
令和5年度各務原市まちづくり活動助成金 取材レポートNO.4

住民が取組む避難所立上げ手順確認事業(八木山自主防災会)

10月8日(日曜日)午前10時~正午、八木山小学校の体育館にて、避難所開設模擬訓練が行われ、メンバー13人と他地域の防災推進員3人、地域住民の応援者5人が参加しました。鵜沼中学校を通してボランティア募集を行い、生徒1人と保護者1人の協力を得ることもできました。訓練には岐阜大学特任准教授の村岡治道さんが立ち合いました。
避難者の受け入れ訓練で、参加者達は事前に決めた「避難所の間取り」に沿って避難所を開設。受付は地区ごとに行いました。受付では予め避難者役に設定した「ペット連れ」「妊娠中」「集団生活が難しく車で生活希望」など個々の状況を把握し案内しました。受け入れ訓練後は、防災対策課職員からマンホールトイレの設置・維持管理や、通信手段の確保、食料の備蓄などの説明がありました。
終了後、メンバーたちは、模擬訓練で気付いたことや改善点を話し合いました。村岡准教授は、「若い人たちにも興味をもってもらえるような工夫をして、参加住民を増やしていくことが課題です。ぜひ、八木山の取り組みや教訓を他の地域にもおすそ分けしていただき、ブラッシュアップのきっかけにしてください。」と話されました。
地域の伝統芸能和太鼓の継承と地元愛の育成事業(各務原太鼓保存会)

10月14日(土曜日)正午~午後1時、コミュニティ炉端にて、各務原太鼓保存会が、第4回目の和太鼓作曲ワークショップを開催し、3歳~小学4年生の子ども9人が参加しました。
参加者は、大小さまざまな種類の太鼓の中から好きな太鼓を選び、お手本に合わせて基本的な叩き方を練習。後半は、みんなで楽譜を組み合わせて作曲しました。団体は、予めいろいろなリズムの書かれた紙から2枚ずつ選んで並べると1曲になるように工夫しました。
参加者達は、早川さんの「リズムを組み合わせるといろんな曲ができます。簡単なリズムと難しいリズムを組み合わせて作ってみましょう。」と言うアドバイスを受け、緩急をつけた演奏しやすい曲を作り演奏することができました。初心者にもわかりやすく、「上手にできたね。みんなすごいね。」とたくさん褒められるので、参加者は楽しんで演奏している様子でした。
防災連絡協議会事業(川島防災クラブ)

10月28日(土曜日)午前10時~午後4時、川島ライフデザインセンターのクラブ・サークル発表会において、川島防災クラブが展示・発表の機会を得て「みんなで防災!」を開催しました。
展示では、団体がこれまでに調査した危険個所の地図や、川島連合自治会内の防災備品の設置状況一覧を展示。水害DVDの上映など、動画でも災害への備えの必要性について知る機会を提供されました。また、防災クイズやアンケートも用意し、参加した家族に粗品を進呈するなどして参加を促しました。ブースは風船装飾により子どもたちの目につくように工夫され、親子が積極的に参加する様子が見られました。
ワークショップは、非常食の試食体験や、災害・避難カード作りを行いました。非常食の体験では、アルファ米に湯を注ぎ、待つ間の15分間には防災士資格を持つ脇田さん・水野さんの主導で、日頃の備えについて話す場が持たれました。「ご自宅で、避難袋は用意されていますか。」という問いに対し、参加者が自身の備えを振り返りました。水野さんは参加者に対し、「アルミフィルムとダンボールがあれば温かく過ごすことができますよ。」「最近はレトルトなども充実していて期限も長いので、日常に取り入れて、使ったら買う、という習慣をつけるといいですよ。」などの具体的なアドバイスを行っていました。
ミニSLによる三世代交流再開事業(ミニSL各務原)

10月28日(土曜日)午前10時~午後3時、川島ライフデザインセンターのクラブ・サークル発表会で、ミニSL各務原も発表団体の一つとして、来場者に対してミニSL乗車体験を提供しました。
来場者は地元住民が多く、団体メンバーと普段から自治会や子ども会などで関係がある親子は、乗車時にも近況を報告し合うなど、コミュニケーションの機会にされていました。SLの蒸気を触ろうとする子どもに注意喚起が必要となる場面もありましたが、保護者は「近くで蒸気や煙に触れる機会はあまりない。蒸気が熱いということを知る機会になってよかった。」と体験により子どもたちが得られた学びを喜んでいました。
11月12日(日曜日)午前10時~午後3時には、河跡湖公園でサクラビマルシェが主催する「おとぎの森deサクラビmarche’ VOL.3」に協力し、サクラビマルシェ内での三世代交流の場を提供しました。子連れの保護者は、「こうしたマルシェでは子どもの楽しめる場が少なくなる傾向があるので、子どもが喜ぶ場があり、家族みんなが楽しいと思えることが嬉しい。」と話していました。
いのちのつながりフェス事業(性教育団体「いのちの授業」ここいく)

10月28日(土曜日)および11月4日(土曜日)、性教育団体「いのちの授業」ここいくによるいのちのつながりフェスが開催されました。
10月28日(土曜日)午後6時~8時は、桜体育館において太鼓演奏を行うたまっ子座と、その子どもロックバンドBaby boomのライブと、「いのちの樹形図づくり」が行われました。
ライブは、来場者に観覧無料で提供。「ラッキーガール」という曲では、自分が自分として生を受けたこと自体がラッキーであるという、作曲者自身がいのちの授業を受けて得た視点を明るい旋律に乗せて伝えられました。
ライブの後には、団体メンバーが「いのちのまつり」という絵本の群読を行い、ひとりの命に至るまでに関係する命のつながりを示す「いのちの樹形図」を説明しました。来場者は、用意された紙に顔を書き、7世代前(江戸時代)まで命を遡ってできる樹形図を手分けして制作しました。
1人・2人・4人・8人・16人・32人・64人・128人と、合計255人の命をつなぎ合わせ、その大きさを感じました。

11月4日(土曜日)午前10時~午後3時は、市民公園においてオーガニックマルシェと「いのちの授業」が行われました。
当初、10月15日(日曜日)の開催を予定していた「いのちの授業」でしたが、天候不順により延期しての開催でした。いのちの始まりのお話、出産のお話、成長する体の仕組みのお話、性の多様性と心のお話、食育のお話の5つの「いのちの授業」が設けられ、各ブース7回の授業を20分ずつ同時多発的に行いました。事前予約を行った方を中心に、未就学児から大人までの幅広い参加者が参加しました。
「いのちの授業」の参加者にはスタンプラリーの用紙が配られ、3つ以上のブースで授業を受けた参加者にはプレゼントも用意されました。各ブースでは卵生と胎生、出産の方法、性器の呼び方や二次性徴、受精について明るく正しく学ぶ機会が設けられ、性には多様性があることや、健やかに成長する為に食の安全性を気に掛ける必要があることなども含め、「生きること」を伝える「いのちの授業」を行いました。
「いのちの事業」ブースの近くでは、オーガニックマルシェが開催され、身体や環境に配慮した商品を扱う13のブースが場を盛り上げました。マルシェを楽しんだ親子や、公園に遊びに来た方々が、「何をやっているのだろう」と授業を後ろから覗いて興味を持つなど、屋外ならではの広がりが見られました。
大規模災害時における避難行動要支援者に対する避難支援訓練事業(鵜沼南町自主防災組織)

11月4日(土曜日)午前10時~午後0時10分、鵜沼南町会館において、鵜沼南町自主防災組織の避難支援訓練と役員会が開催され、15人が参加しました。
避難支援訓練には、東部方面消防署みどり坂出張所の職員3人が立ち合い、担架を使う搬送技術や毛布などを担架の代わりに使う方法などの指導に当たりました。
訓練は、リヤカーを組み立てることから始め、簡易担架を使った搬送訓練を行いました。担架で搬送した要支援者をリヤカーに乗せてみたところ、寝た状態では足が大きくはみ出し、安定して運ぶための方法が話し合われました。
ソフト担架を使った搬送では、室内階段と非常階段を下りてみて、メンバーが搬送するのは厳しいことがわかりました。消防署の職員は、「皆さんだけで搬送するのは体力的に難しいと思います。ぜひ、若い人を巻き込んでください。皆さんは、知恵と指示を出す役割をお願いします。今日の訓練で出た課題を検討していただき、今後も積極的な訓練を行ってください。」と講評しました。
おいしく食べていっぱい遊ぼう事業(結愛ポート)

11月26日(土曜日)午前10時~午後3時、総合福祉会館において、「にこにこフェス」が開催されました。「自然物」「紙工作」「毛糸・布」「スライムづくり」「折り紙」「バルーンアート」「べんがら染め」「防災クッキング」の8つのブースが用意され、団体メンバーや他団体からの協力者も含め多数の大人と子どもがスタッフとなり、参加者の活動を見守りました。スタッフの子どもたちは、当日の受付などのほか、会場ポスターの絵を描くなど事前準備から関わりました。
各ブースでは必要最低限の情報提供に留めることで、「自分のやりたいことを自分で決めて思い切り楽しむ場」を意識され、子どもたちはそれらを自由に組み合わせて楽しみました。防災クッキングでは、炊飯と蒸しパン作りを提供する傍ら、けんちん汁を用意。参加者の親子はお腹を満たして再び遊び、充実した一日を過ごしました。
決まりごとの少なさに戸惑う参加者もありましたが、代表の各務さんは、「決められたことをこなすだけでは、子どもの体験にならないので、この場を用意できてよかったです。」と力強く話しました。
令和5年度各務原市まちづくり活動助成金 取材レポートNO.3
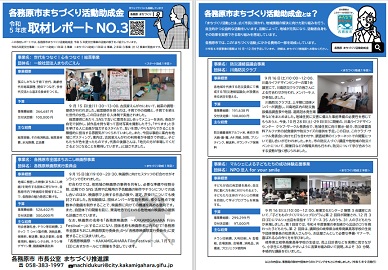
世代をつなぐ!心をつなぐ!総菜事業(一般社団法人まちのごえん)

9月15日(金曜日)午前11時30分~午後1時、古民家えんがわにおいて、総菜の調理・提供が行われました。総菜提供を担うのは、子育て中の母親と、子育てを終えた世代の女性。この日は合計8人体制で実施されました。
総菜提供にあたり、SNSで互いに意見を出し合ってメニューを決め、各自が自宅で試作し、試作品を持ち寄って宣材写真を撮影したそう。「やります」と手を挙げる人に全員が協力するスタイルで、互いを思いやりながらできることを積極的に担当する雰囲気がつくられていました。また、今回は事前に案内を地域にポスティング。案内は、古民家えんがわの利用者が手描きで作成し、子どもたちが色を塗ったものです。代表の後藤さんは、「地元の方が来場してくださるようになることを期待しています。」と話されました。
各務原市全国まちおこし映画祭事業(各務原映画祭実行委員会)
9月15日(金曜日)午後7時~8時30分、映画祭に向けたスタッフの打合わせがオンラインで行われました。
打合わせでは、他地域の映画祭の事例を共有し、必要な準備や役割分担、広報でのSNS活用や広報用の予告動画の制作やチラシについての話し合いのほか、映画祭で上映する作品の数や、選定、声掛けについても検討されました。告知動画は、団体メンバーが監督を務め、さまざまな視点で複数本の動画を制作することで、映画祭に向けての機運を高める意向です。また、自団体での開催を前に、東海地方で行われる他地域の映画祭の視察も計画されています。
なお、映画祭の名称を「各務原映画祭 ~KAKAMIGAHARA Film Festival~」とすることになり、団体名称も映画祭名に合わせて「各務原市全国まちおこし映画祭実行委員会」から「各務原映画祭実行委員会」に変更することに決まりました。
「各務原映画祭 ~KAKAMIGAHARA Film Festival~」は、1月7日(日曜日)にあすかホールにて開催を予定しています。
防災連絡協議会事業(川島防災クラブ)

9月16日(土曜日)午前10時~正午、川島ライフデザインセンターの第1会議室にて、川島防災クラブの皆さんによる打合わせが行われ、メンバー9人が参加しました。
川島防災クラブは、上半期に団体メンバーが調査し、川島地区内の防災施設備品調査表や地図、道路冠水発生場所などをまとめました。地域住民に災害に備えた事前準備の必要性を感じてもらおうと、今後、10月28日(土曜日)・29日(日曜日)に開催の、川島ライフデザインセンター クラブ・サークル発表会で、地域住民に向け展示・紹介、防災備蓄食料アルファ米の試食提供や防災クイズの提供を予定。この日は、このクラブ・サークル発表会に向けた打ち合わせや、調査結果のインターネットでの閲覧について話し合いが行われました。
また、市の防災人づくり講座や他地域の防災イベントについて、開催日などの情報共有も行われ、防災について学び合おうとする姿勢が強く感じられました。
マルシェによる子どもたちの成功体験応援事業

9月16日(土曜日)午前10時~正午、産業文化センター2階第3会議室において、「子どもものづくりマルシェプログラム」の第2回目が開催され、12月3日(日曜日)にマルシェ出店を目指す17ブース35人のうち、31人の子どもたちが来場しました。第1回目では、令和4年度事業の参加者から出店のコツを教わった子どもたち。第2回目は、講師役の岐阜県立岐阜商業高等学校の生徒や団体理事長の松原英人さんから、お店屋さんとして必要な準備・マナーや、喜ばれる心の作り方を学びました。
岐阜県立岐阜商業高等学校の生徒は、売上日計表などを実際に見せながら、小学生にも理解しやすいように言葉を噛み砕いて説明。およそ30分間、本格的な講座を行いました。
令和5年度各務原市まちづくり活動助成金 取材レポートNO.2
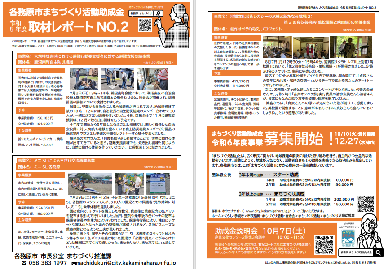
大規模災害時における避難行動要支援者に対する避難支援訓練事業(鵜沼南町自主防災組織)

7月2日(日曜日)午後1時~2時、鵜沼南町会館において、鵜沼南区の自治会役員と鵜沼南町自主防災組織との顔合わせ会と、役員会が開催され、訓練計画の詳細について検討されました。
当日は、早朝から自治会による地域清掃が行われており、地域清掃終了後の午前10時~正午には、自治会長と自主防災組織のメンバー合わせて30人が、一緒に炊き出し訓練を行いました。今後、区民全体で11月に避難支援訓練、12月に炊き出し訓練を行う予定です。
令和5年度で開始から5年目となる炊き出し訓練では、新しく着任した自治会役員に対し、何度も経験を重ねている自主防災組織メンバーが、備品の保管場所や炊き出し準備の手順をレクチャーする様子がありました。
事務局の大竹さんは、「何度も繰り返し経験することで、実際に動ける体制が出来てきていると思う。避難支援訓練でも、炊き出し訓練と同じように、自然に動ける体制を作っていきたい。」と感慨深そうに話されました。
ミニSLによる三世代交流再開事業(ミニSL各務原)

7月29日(土曜日)午前9時~正午、子苑第一幼稚園の「苑遊会」が行われ、ミニSL各務原のスタッフ7人が、310人の園児とその保護者・兄弟姉妹に対し、ミニSL乗車体験を提供しました。
園の意向で、チケットを購入した枚数分、乗車後に乗車記念の缶バッチを配布する形式で行われました。当日、整列や乗車後の缶バッチの配布は保護者役員や先生方により行われました。保護者役員により、独自にチケットや運休中となった場合の整理券が準備されるなど、各所にスムーズな乗車体験となるような工夫が見られました。
乗車に当たり、園児とその保護者がミニSL各務原のスタッフと触れ合う様子があり、缶バッチを受け取った園児は、「公園で見たことがあるけれど、幼稚園に来てくれて嬉しかった。また乗りたい。また来てね。」と話していました。
地域文化芸術レガシーの承継と新たなる挑戦2:第2回貞奴芸術祭(萬松園編と映画編)の開催事業(創作オペラ「貞奴」プロジェクト)

8月7日(月曜日)午後0時30分~3時40分、迎賓館サクラヒルズ川上別荘「萬松園」において、「第2回貞奴芸術祭~萬松園編~」が開催されました。定員30名のチケットは、事前に完売しました。
数名ずつに分かれ萬松園をガイド付きで見学後、桐の間にて、「貞奴さんの美学に触れる~和洋の交錯~」というテーマで高北幸矢さんのアートトークが行われました。
次に、各務原×茅ヶ崎と題したミニコンサートが行われました。代表の金光さんや、元茅ヶ崎市「音貞オッペケ祭」実行委員の清水友美さんら演者4人が、貞奴にちなんだ歌や演奏を披露し観客を魅了しました。
観客からは、「貞奴さんへの思いが込められた歌が聴けて、感動しました。萬松園で開催することに意味があるんですね。貞奴さんも喜んでいるでしょうね。」という感想がありました。
令和5年度各務原市まちづくり活動助成金 取材レポートNO.1
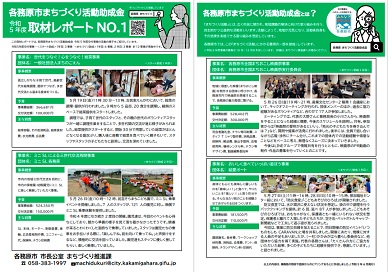
世代をつなぐ!心をつなぐ!総菜事業(一般社団法人まちのごえん)

5月19日(金曜日)午前11時30分~午後1時、古民家えんがわにおいて、総菜の調理・提供が行われました。9時から5品目、20食分を調理し、縁側のスペースで総菜提供をスタートしました。
調理では、子育て世代のスタッフと、その親の世代のボランティアスタッフが一緒に調理作業をすることで、多世代間の交流が進む様子がみられました。総菜提供がスタートすると、開始30分で用意していた総菜がほとんどなくなる盛況ぶり。購入後に座敷で総菜を食べていく親子もいて、スタッフやスタッフの子どもたちと談笑し、交流を深めていました。
ミニSLによる三世代交流再開事業(ミニSL各務原)

5月26日(金曜日)午前10時~正午、前宮そらまちこども園で、ミニSL乗車イベントを開催しました。7人のスタッフが、121人の園児に対し、無償でミニSL乗車体験を提供しました。
令和4年度に引き続き2度目の開催。園児達は、今回のイベントを心待ちにしており、朝から準備の様子を見て落ち着かなかったそうです。順番が来るとわくわくした面持ちで乗車していました。スタッフは園児たちの乗車をお手伝いする際に、「楽しんでね。前を向いて乗ってね。」と声掛けをするなど、積極的に交流を図っていました。園児達もスタッフに優しく接してもらい、楽しく乗車していました。
各務原市全国まちおこし映画祭事業(各務原市全国まちおこし映画祭実行委員会)

5月26日(金曜日)午後7時~9時、産業文化センター2階第1会議室において、キックオフミーティングが行われ、団体メンバーのほか、過去に協力経験があるボランティアなど、合わせて17人が参加しました。
ミーティングでは、代表の大野さんと事務局長の小川さんから、映画祭をやることになった経緯と概要、今後のスケジュールを説明し、共有。参加者からは「映画祭の愛称があるといい」、「地元の子どもたちを巻き込んでは?」など、質問や提案が活発に行われました。後半には、全員で話し合いながら広報・渉外にチーム分け。これまでの団体内での活動経験や得意なことなどをベースに考え、無理なくスムーズに決まっていきました。
今後はSNSグループ内で情報共有を行うとともに、映画祭のPR動画の制作・作品の募集を行っていくとのことです。
おいしく食べていっぱい遊ぼう事業(結愛ポート)

5月27日(土曜日)午前11時~午後4時、5月28日(日曜日)午前10時~午後3時、那加福祉センター前において、「防災食堂」、「こどもあそびのひろば」が開催されました。
防災食堂では、水が潤沢に使えない状況を想定し、袋の中で調理を行うパッククッキングを提供。計6回、延べ84人が参加しました。こどもあそびのひろばでは、おもちゃがなく、保護者とも一緒にいられない状況を想定。保護者と離れて入場した子どもたちが、空き缶・ペットボトルキャップ・新聞紙などで工夫して遊ぶ姿が見られました。
今回は、事業に防災目線を加えることで、同日開催の防災イベント「いつものもしもCARAVAN」と場を共有しました。開催にあたり、規模に対する人員の不足もありましたが、一般社団法人かかみがはら暮らし委員会など、他団体から協力を得て実施。代表の各務さんは、「たくさんの方にご協力をいただいた結果、多くの子どもたちに経験を提供でき、感謝しています。」と話されました。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課
電話:058-383-1997
まちづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
