令和6年度交付事業取材レポート
取材レポートでは、各務原市まちづくり活動助成金 令和6年度交付事業の活動の様子を紹介します。(レポートの内容は、事務局の取材や団体からのヒアリングなどをもとに作成します。)
住民が取組む避難所立上げ手順確認事業(八木山自主防災会)
防災キャンプin八木山

1月12日(日曜日)午前10時~午後3時、八木山小学校の体育館にて、「防災キャンプin八木山2025」が行われ、メンバー13人と、他地域の防災推進員1人、地域住民の応援者30人が参加しました。今回も自主防災会は鵜沼中学校を通してボランティア募集を行い、生徒18人と保護者100人の協力を得ることができました。また今回は、国土交通省中部地方整備局から車両2台(対策本部車・照明車)が展示され、国土交通省中部地方整備局中部技術事務所から6人が来場されました。
今回のイベントでは、「楽しく防災体験をしましょう」と言う発想が取り入れられ、子どもさんが楽しめるドローン体験や遊びコーナーが設けられました。また、国土交通省中部地方整備局の車両2台にも多くの人が集まり、対策本部車(13畳の広さになる)に搭乗したり、照明車(10メートル級)のリモコン操作を体験しました。
予行訓練を実施

12月14日(土曜日)正午~午後1時、つつじが丘集会場において、1月に「新春の集い」と同時開催する防災イベントに備え、八木山自主防災会のメンバー9人による予行訓練が行われました。訓練では、最初にガソリンを使用した発電機の使い方を練習しました。発電機は重いため、荷台に最初から設置しておく工夫が見られました。また、初めて使う方でも迷わないようにマニュアルをラミネート加工して土台に備え付けました。使用後のガソリンの処理や、オイルの交換、清掃などについても共有され、「慣れていないと、いざというときに活用ができないので、定期的に使う機会を設けよう。」という話し合いがされていました。発電した電気を多くの用途に使うためのタップや、電気を貯めておくための蓄電池などについても必要性が検討されていました。
発電機が無事使えることを確認した後には、防風タイプの屋外用カセットコンロを使って湯を沸かし、防災食のお米を試しました。水で作ったもの、湯で作ったもの、置いておく時間などに差をつけ、メンバーがそれぞれの違いを確認しました。
今回の訓練結果を、防災イベントでの展示や情報提供に活用されるということです。
大規模災害時における避難行動要支援者に対する避難支援訓練事業(鵜沼南町自主防災組織)
搬送訓練を実施

1月11日(土曜日)午前10時~11時、鵜沼南町会館において、鵜沼南町自主防災組織の避難支援訓練と役員会が開催され、消防団2人を含む10人が参加しました。
訓練は、備品の在処を確認するところからスタート。本部長の大竹さんの呼びかけのもと、各自が分担して、リヤカーの組み立てや担架の準備を行いました。
令和6年度の搬送訓練では、担架で搬送した要支援者をリヤカーに乗せる際、寝た状態では足が大きくはみ出していましたが、今回は安定して運ぶためにべニヤ板を敷き、安定して搬送することができました。
また、令和6年度の搬送訓練で消防職員から提案があった、物干し竿と毛布を使った簡易担架では、参加者から「思ったよりも安定して運べるね。」という感想がありました。毛布や物干し竿は搬送後にも活用ができるため、「もう少し数を用意しておいてもよいかもしれない。」という話し合いも持たれました。
さらに、令和6年度の訓練では、狭い階段の搬送ではソフト担架を複数人で支えることができずメンバーの体力では搬送するのは厳しいとされていましたが、今回はカラビナと搬送用ベルトを併用して複数人に重さを分散させることで搬送が可能になりました。若い消防団メンバーは2人でも搬送可能であることも確認できました。参加者からは「階段を使った搬送には体力も必要なので、力に自信がない人は無理をせず、平面移動を中心に活躍してもらってはどうか。」「階段用のストレッチャーもあるので、今後、検討してはどうか。」「マンション高層階に住む寝たきりの方には自宅避難という形を取ってもらい、人の搬送の代わりに支援物資を運んであげることもできる。」と言う意見が出されました。
本部長の大竹さんは、「別事業で継続している炊き出し訓練同様、搬送訓練も継続し、メンバーや地域住民の中に知識や経験を持つ住民を増やし、災害時に動ける状態にしていきたい。」と話されていました。
各務原映画祭事業(各務原映画祭実行委員会)
第二回各務原映画祭開催

12月22日(日曜日)正午~午後6時30分、産業文化センター1階あすかホールにて「各務原映画祭」が開催されました。
全国から集まった地域映画(まちおこし映画)13作品が、4部に分かれて上映されました。各部が終わるごとに、監督や俳優のトークショーが行われ、来場者は普段あまり触れる機会のない映画製作の裏話などを聞いて楽しみました。会場ロビーでは、過去に団体が制作した市内映画作品の上映と市内ロケ地を紹介したパネルの展示も行われました。
団体メンバーは、12月21日(土曜日)午後5時から事前の打ち合わせと設営を行いました。今回はホームページからの予約システムを導入したので、受付での予約対応が順調に行われるように、メンバー全員に手順を共有しました。
当日は、第1部から第4部まで長時間に渡る上映にも関わらず多くの観客が詰めかけました。トークショーに登壇した映画関係者からは、映画に順位をつけることが無い各務原映画祭のすばらしさを称賛する声が上がりました、また地域映画の役割である「その地域のその時の風景や人々、文化が記録された貴重な映像としてのアーカイブ的な役割」が語られました。
閉会の挨拶では、各務原映画祭実行委員会代表の大野さんが、令和7年度の各務原映画祭実施の意気込みを語られました。
第一回ミーティング開催

6月3日(月曜日)午後7時30分~9時 LINEミーティングで、各務原映画祭実行委員会のメンバー13名による第1回ミーティングが実施されました。
第2回各務原映画祭を令和6年12月22日(日曜日)に開催することになり、第1回各務原映画祭の反省をもとに、上映本数のほか、作品の選定、広報手段、事前予約の有無、必要な作業の分担について話し合われました。
議論を経て、応募条件は「上映時間が30分以内」、「インディペンデント映画であること」、「地域に特化していること」という条件とし、前回上映した監督の推薦作品・映画祭スタッフセレクション・一般公募で受付の作品から9本を選定して上映することになりました。また選定は、作品選出に関わりたい映画祭スタッフで作品選出チームを組み、チーム全員で決定するほか、映画祭スタッフ全員が事前に作品を把握して当日の説明ができるようにされる意向です。
防災連絡協議会事業(川島防災クラブ)
「みんなで防災!」を開催

11月30日(土曜日)午前10時~午後4時、12月1日(日曜日)午前10時~午後3時、川島防災クラブが、川島ライフデザインセンターのクラブ・サークル発表会において、展示・発表の機会を得て「みんなで防災!」を開催しました。
展示では、団体がこれまでに調査した川島全域の道路冠水危険個所の地図・冠水箇所情報や、川島連合自治会内の防災備品の設置状況一覧を展示しました。
- 「道路冠水」に関する調査報告(2023年8月19日作成、2024年11月24日修正)
- 「防災施設備品」に関する調査報告(2024年9月2日作成、2024年10月19日修正)
ワイド画面ディスプレイには、DVD「南海トラフ地震(迫りくる大地震に備える)」が随時放映され、災害への備えの必要性について知る機会が提供されました。また、防災クイズが用意され、参加した家族に粗品(風船・しりべんトイレットペーパー)を進呈するなどして参加を促しました。
減災グッズチェクリストも配布され、“自分の命は自分で守る”ための備えとして、普段から持ち歩きたいもの、災害発生直後に用意する備え、災害発生後の数日間を自給自足するための備え、が分りやすく説明されました。
ワークショップは、時間を定めて「非常食アルファ米の試食体験」や「毛布で作り簡易担架体験」が行われました。
写真展「鵜沼」-空中歩道・鵜沼地区の活性化を目指して事業(住みよいまちづくりを考える会)
歴史講演会「国史跡『坊の塚古墳』~鵜沼に特別な古墳ができる理由~」を開催

令和6年11月23日(土曜日)午後1時から3時半、鵜沼南町会館において、住みよいまちづくりを考える会主催の歴史講演会「国史跡『坊の塚古墳』~鵜沼に特別な古墳ができる理由~」が鵜沼地域のにぎわいの創出と活性化を目的に開催され、鵜沼南町区内から20人、区外から31人の、計51人が参加しました。
坊の塚古墳は令和6年10月に国指定史跡として登録された、鵜沼羽場町にある前方後円墳です。県内2位の大きさを誇り、全長120メートル、3段の古墳ということで、市が行った発掘調査の結果わかったことなどの解説がありました。
石室周りから出土した滑石製模造品の展示もあり、参加者は当時の埋葬や建築技術・製造技術に驚きながら出土品を間近で見学し、学芸員による説明に耳を傾けていました。
講演後には希望する人たちが坊の塚古墳がある羽場町に移動しました。段差の角が崩れている部分もありますが、動かずに残っている基定石をもとに、はっきりと3段であったとわかること、土砂を崩さないため「斜面角度は最大30度」という現代の基準が当時から使われていること、周壕という堀の名残による段差が周辺の家屋などからわかることなど、解説を聞きながら見学しました。参加者からは、「こうした魅力が知られて、管理をする人が増えるとよい」、「犬山から鵜沼観光につながるとよい」などの声があり、令和7年度の企画にも期待されていました。
表彰式を開催

令和6年10月6日(日曜日)午後2時から3時、鵜沼空中歩道 中央昇降口2階広場において、住みよいまちづくりを考える会主催の写真展「鵜沼」の表彰式が行われました。
8月から「各務原」をテーマにした写真を募集し、近隣住民や市民カメラマン、時々各務原市を訪れる方などからおよそ100点の写真が集まったほか、鵜沼第一小学校や各務原市文化財課、犬山市などからも古い写真が貸出されました。
この日は鵜沼空中歩道にある14枚のパネルに、最優秀賞1点、優秀賞2点、佳作10点、特別賞1点が掲示され、入賞者が家族と共に会場を訪れ、写真について尋ねたり、記念撮影などをする様子が見られました。
今後、写真は順次入れ替えされながら、応募作品すべてが展示される予定です。11月23日(土曜日)には鵜沼南町会館を会場に各務原市文化財課職員による歴史講演会も予定されており、講演会の後には地域の史跡散策も行われるとのこと。代表の大竹さんは、「たくさんの方に鵜沼を楽しんでいただきたい。皆様、お時間の許す限り、ぜひお越しください。」と参加を呼びかけられました。
展示写真の応募を受付
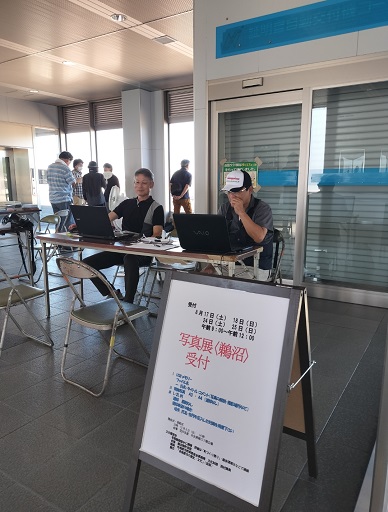
8月17日(土曜日)午前9時~正午、鵜沼空中歩道 中央昇降口2階広場 において、住みよいまちづくりを考える会のメンバーなど12人により写真展「鵜沼」の展示写真の受付が行われました。
JR鵜沼駅と名鉄新鵜沼駅をつなぐ空中歩道の中央昇降口より南側は、電車を乗り継ぐために往来する人々にとって通らなくても済んでしまう場所であるため、通る理由が必要になります。また、地域住民にとって駅は通過点となっており、空中歩道がこのように活用できる場所であることを知らない人も多くいます。団体はここに住民などから募った写真を展示することで、空中歩道ににぎわいをもたらそうと、10月6日(日曜日)から写真展を予定しています。
この日は6件の応募があり、犬山側から鵜沼南町の風景を撮ったものなど、本格的な写真が集まりました。団体は、大きく印刷した写真を持参する方、スマートフォンからデータを提供される方など、応募する方のニーズに合わせて複数の応募方法に対応しました。
写真を応募した女性は「日頃、歩いていて素敵な景色に遭遇すると、スマートフォンで撮影するようにしています。今回は広報紙に掲載されている記事を見て来場しました。自分が見た景色を皆さんに見てもらえるのは嬉しいです。」と話しました。また、応募者の一人である尾崎さんは、「普段『市民カメラマン』としても活動しています。今回、自治会の区長を担っていたので回覧に気が付いたけれど、普段だと見落としてしまうところ。大変だと思うけれど、周知を工夫されれば、もっと応募につながるのでは。」と期待を込めて話しました。
写真の受付は、8月18日(日曜日)、24日(土曜日)、25日(日曜日)にも同じ時間、同じ場所で行われます。
各務原市立那加中学校ビオトープ再整備事業(つゆ草の会)
企業ボランティアと一緒に整備活動

11月18日(月曜日)午後2時~4時、那加中学校ビオトープにおいて、岐阜トヨペット株式会社のボランティアスタッフ25人と団体メンバー5人がビオトープの草抜きなどの整備活動を行いました。
団体は、10月19日(土曜日)に中学生とともにチューリップなどの苗植えを行い、ビオトープは春に向けた準備が始められていました。この日は、コスモスが咲き終えたエリアで枯れた葉などを取り除いたほか、苗の間に生えている雑草を抜く、落ち葉を集める、下草に覆われた芝桜の手入れをするなどの作業が行われました。およそ2時間の作業でしたが、若いボランティアたちの手であっという間に雑草が取り除かれていく様子に、団体からは「若い方の力をお借り出来てありがたい。」と感謝の言葉がありました。
また、整備の途中には中学生5人が、ビオトープで実ったミカンを収穫したり、アイガモにえさを与えたりしながら、団体メンバーと談笑する様子が見られました。団体代表の金原さんは、「卒業しても、学校関係者でなくても、ビオトープがあることでつながり続けられる。近くに来た時には、ビオトープにぜひ立ち寄って欲しい。」と話されていました。
市民交流スペースで春らんまん写真展を開催

6月27日(木曜日)午前9時~11時、市役所本庁低層棟1階の市民交流スペースでつゆ草の会による「那加中学校ビオトープ 春らんまん写真展」の展示作業が行われ、団体メンバーのうち、写真展を担当する5人が協力して作業を行いました。
今回の写真展では、春の写真50枚が展示されました。一部の写真には「気に入った写真にシールを貼ってください」と黒台紙やシールが添えられ、観覧者が気に入った写真に投票することでビオトープの存在をより意識できるよう工夫されました。
中央図書館ロビーにて那加中学校ビオトープ写真展を開催

6月19日(水曜日)午前9時~10時、中央図書館1階のロビーでつゆ草の会による「那加中学校ビオトープ写真展」の展示作業が行われました。
今回の写真展は「春のビオトープの紹介」とのことで、チューリップや桜、ホタルやカルガモの写真、夜のライトアップをした幻想的な風景写真など、たくさんの作品の中から厳選された18枚を7月4日(木曜日)の午後4時まで展示します。
展示に際し、図書館に入ってきた方、図書館を利用し終えて外に出て行かれる方の動線を考えてレイアウトを決定。図書館利用者の妨げとならないよう、事前に施設側と打ち合わせを行ったうえで、パネルの両面を使ったり、椅子の配置も調整して、多くの写真をゆっくり見てもらえるよう工夫されました。
また今後は、6月27日(木曜日)から7月9日(火曜日)まで市役所本庁舎低層棟の市民交流スペースでの展示も予定しています。
那加中学校ビオトープ 蛍の幼虫を放流

4月7日(日曜日)午前9時~10時、那加中学ビオトープ「那加庭」にて、蛍の放流式が行われました。
桜・チューリップ・芝桜が美しく咲くビオトープ「那加庭」に、つゆ草の会の皆さん(14名)・生徒会執行部の皆さん(5名)・地域の皆さんが集まり、つゆ草の会の皆さんが育てられた500匹の蛍の幼虫を、参加された皆さんの手で放流しました。
6月頃には、蛍の幼虫が蛹から羽化して夜空を舞う予定です。令和5年は約200匹が羽化したので、令和6年は300匹が羽化することを皆さん期待されています。
(注)「ビオトープ」ですが、令和5年度、那加中学校の生徒さん達の校内公募により「那加庭」と命名されました。学生さん達は「那加庭」と呼んでおられます。(生徒会長さん談)
会の終わりには「サプライズイベント」として、生後一か月の鴨の赤ちゃん(8羽)のお披露目が有りました。立派な鴨に成長することを皆さん期待されています。
対話の本質を探りコミュニケーション力を高める事業(岐阜友の会)
おとなかいぎ(12月)

12月5日(木曜日)午前10時30分~11時30分 岐阜友の会が、各務おがせ町の「古民家えんがわ」で、一般社団法人まちのごえんが開催する「えんがわ親子サロン」とのコラボ企画として「おとなかいぎ」を開催しました。
参加者は、来場したお母さん4人、そのお子さん6人、岐阜友の会のメンバー3人、一般社団法人まちのごえん1人の計14人が、クリスマスリースを作りながら、楽しく意見を交換しました。
岐阜友の会のメンバーから参加者に「本日は、親子サロンでクリスマスリースを作りながら親子で楽しみましょう。そして、おとなかいぎをしたいと思います。子育て中の皆さんと、子育て中の身近な思いをみんなで共有したいと思います。」と説明があり、かいぎがスタートしました。
岐阜友の会の皆さんは、生後3か月の赤ちゃんを抱いたり、生後11か月の男の子の面倒を見たり、子ども達にクリスマスリース作りを指導したりして、お母さんたちが少しでもおとなかいぎに参加できる時間を作ってあげました。お母さんたちは、子どもたちを遊びに連れていっている場所の話、子どもたちの食事の話、子どもがケガをしない見守り方の話、感染病から子どもを守る話、つかまり立ちの話、こどもの体重の話など、いろいろな話題について意見を交換しました。岐阜友の会のメンバーは、自分たちの子育て経験談を交えながら、お母さんたちが話しやすい雰囲気作りを心掛け、お互いの意見や立場を尊重して、話す側と聞く側がストレスなく意見交換ができる円滑なコミュニケーションの場を提供しました。
おとなかいぎ(10月)

10月19日(土曜日)午前10時~11時、 鵜沼各務原町のカフェGA楽(がらく)で「おとなかいぎ」が開催され、参加者9人と岐阜友の会のメンバー3人の計12人が「子ども会のあり方」や「これからの運営方法」などについて意見を交わしました。
初めに地域の小学校で育成長を務める参加者から子ども会の現状について話があり、「子ども会に加入しない家庭が増えたが、今後どのように存続させていくのがよいでしょうか。」と話題が投げかけられました。
「役員の負担軽減ができれば子どもたちは戻ってくるのでは。」という意見に対し、小学生の子を子ども会に参加させていないという参加者は、「ちょっと違う」と、参加させていない理由について話し、子ども会ではない場でのボランティアには積極的に参加していることを伝えられました。他の参加者からは「地域という強制的なつながりがなければ出会うことがない人もいる。」、「習い事など、他の取り組みに重点を置く保護者も多い。子ども会も習い事と同列で『子どもにどのような経験をさせられる場か』が見られて、取捨選択の対象になっているのでは。」といった意見が出されました。
これらの意見を経て、「ただ保護者が用意する慣習的なイベントに参加するだけ、という形から脱却してもよいのでは。」、「例えば子ども会に入ると大学生と一緒にやりたいことを自分たちで企画するという経験ができる、となれば、参加させたいと思う保護者もいるのでは。」、「無理に人数を増やさず、そのコミュニティをいいと思う人たちが魅力的だと思える活動をしたらよいのでは。」などと、新しい子ども会のあり方や明るい展望について話し合われました。
また、「まずはクリスマスと2月の行事をどのように運営しようか迷っています。お金はあるけれど人手は足りないので、みなさん、助けていただくことはできませんか。」という具体的な相談もあり、参加者からは活動例などの情報提供や、協力の申し出がありました。
おとなかいぎ(9月)

9月14日(土曜日)午前10時~11時 各務原市民公園の茶室「各務野」で、岐阜友の会(4人)が「おとなかいぎ」を開催しました。
「おとなかいぎにに参加しませんか」・「子どもたちの聴く力、話す力、理解力、表現力、創造力について話しませんか」とチラシやSNSで呼びかけ、3人の参加がありました。
岐阜友の会(4人)と、参加者(3人)で、おとなかいぎ(計7人)を実施しました。
まずは、全員で、8月10日(土曜日)に中央図書館多目的ホールで開催された映画「こどもかいぎ」にて参加者が付箋に書いた感想コメントを読み、映画の主題である「こどもから学ぶ対話の本質や重要性」を再確認しました。
今回のおとなかいぎは「こどもの居場所」、「こどもとのコミュニケーションの取れる場所」についての話合いの場所となりました。こどもの居場所として子ども食堂が大切である話や、食べ物を提供するだけでは会話がなくなるので一緒に食べ物を作る工程を共有することでコミュニケーションが生まれることを話しあいました。市外の学童保育ではボランティア学生が協力をして子ども達の居場所を提供している話が出ました。
岐阜友の会からは、外国人の若者が日本語に馴染んでコミュニケーションを取れる支援をしている市外の事例が紹介されました。
「こどもかいぎ」上映会

8月10日(土曜日)午前10時~午後3時30分、中央図書館多目的ホールで、岐阜友の会が映画「こどもかいぎ」の上映会と「こどもかいぎ」を実施しました。午前・午後の部で、こども32人・大人118人の計150人が参加しました。
岐阜友の会のメンバー15人が、各人の担当ごとに、参加者のホールへの誘導、司会進行、映画のプロジェクターへの投影、ホール内の音声音量調整・照明調整を行いました。また、各務原市民公園内の茶室(各務野)では保育士2人とボランティア4人の計6人が参加者からの依頼を受けて託児を行いました。
映画「こどもかいぎ」は、子どもたちが「かいぎ」をする保育園を1年間に渡って撮影したドキュメンタリー映画です。子どもたちの「かいぎ」には、明確な答えも結論もありませんが、全力で話し合い、遊び、泣き、笑いながら社会とつながろうとしているこどもたちの姿がありました。彼らの、まっすぐな言葉や、奇想天外な発想は、時に大人の心を打ち、笑いを誘いました。「どうして生まれてきたんだろう?」「ケンカしないようにするにはどうすればいいの?」と言った問いかけや、思わず微笑んでしまうような発言もあり、観る人に新たな視点を提供してくれました。保育園は子どもたちが初めて社会と接する場所であり、そこで繰り広げられる「こどもかいぎ」は、現代社会で私たちがどう生きていくべきかを考えるヒントを与えました。
映画「こどもかいぎ」の上映後、会場では岐阜友の会のメンバーが司会を務め、子どもたちと保護者が5〜6人のグループに分かれて感想を語り合いました。子どもたちからは「友達ともっと仲良くするにはどうすればいいか」という問いや、「大人ももっと話し合った方がいい」という意見が出ました。保護者たちは「自分たちの子どもの頃にはこのような場が少なかった」「少人数での話し合いが効果的だ」「家庭でも子どもを一人の存在として尊重し対話を重視したい」という意見が多く出ました。また、保育士や教育関係者からも「子どものペースを大切にする保育の重要性を改めて感じた」「映画の内容が現場にとって大変有益である」という声が出ました。
参加者達にとって、映画「こどもかいぎ」を鑑賞し、「こどもかいぎ」を体験することは、対話の本質や重要性を考えるきっかけになりました。
「こどもかいぎ」上映会に向けたテスト上映

5月16日(木曜日)午後4時~5時 中央図書館多目的ホールで、岐阜友の会(6名)が、8月10日(土曜日)の映画「こどもかいぎ」上映会に向けたテスト上映を実施して、ホールの使用状況を確認しました。
岐阜友の会のメンバーが、DVDの動作確認、パソコンからプロジェクターへの接続確認、プロジェクターからスクリーンへの投影確認を行い、画像調整や音の調整を行いました。
また、客席の後ろにあるコントロールルームでコントローラーの使い方を教わり、マイク音量調整や照明の明暗調整を確認しました。
上映会の参加者は幼児から中高年と年齢幅が広いので足元の照明の調整を注意深く行い、妊婦の方や乳幼児を抱いた女性がすぐにホールから退出できるよう入口付近の席の確保も検討しました。
いのちのつながりフェス事業(性教育団体「いのちの授業」ここいく)
出演者との打ち合わせを実施

9月16日(月曜日・祝日)午前10時~午後4時、産業文化センターあすかホールにて、「性教育団体『いのちの授業』ここいく」の主催で「いのちのつながりフェス」が行われ、およそ250人が来場しました。
当日は2回のスペシャルライブがあり、午前11時~正午のステージは「いのちのはじまり」をテーマに、また午後2時~3時のステージは「多様性」をテーマに構成されていました。歌手の木歌さんの歌声、絵本ソムリエールのわかさんの絵本パフォーマンス、ここいくのパネルシアターや語りなどを組み合わせながら、来場者に自然に「いのちのつながり」や「人権」について考えるきっかけを提供されました。
午前のあいさつで、団体代表で助産師でもある中村暁子さんは「文科省の規定により、学校の授業では具体的な性交を教えることができないけれど、子どもたちはインターネットで偏向的な情報を見ることができてしまう。私たちは性について正しい知識を丁寧に伝えたいと思っています。」と話し、スペシャルライブの中では幻想的な歌に合わせて「すべての生き物は、生活環境に合わせた仕組みで命をつなげています。」と卵巣・精巣の存在について具体的な言葉で分かりやすく伝え、卵子・精子の出会いの場面もイメージしやすいよう布や模型を使って表現しました。
卵子と精子が出会ったあとに母体の中で胎児が大きくなっていく様子は、わかさんによる絵本の読み聞かせで伝えられました。その後、木歌さんの歌に合わせて、関係者から募った生まれたばかりの赤ちゃんの写真がスライドで上映され、来場者がそれを見ながら涙ぐむ場面、子どもが母親に抱き着く場面も見られました。
後半は、ここいくによる、ランドセルの色や服の選び方を話題にした多様性のパネルシアターから始まり、グーチョキパーを例に「誰もが強くも弱くもある」ことも伝えました。わかさんによる絵本パフォーマンスでは結婚観の多様性にも触れ、複数の絵本をリズミカルに組み合わせながら読むことで、みんな同じでみんな違う、いろいろな側面があること、みんな生きていることを、鼓動に見立てた太鼓による効果音も交えながら伝えました。最後には木歌さんが「輪」をイメージした歌を歌い、それに合わせて関係者が布やダンスパフォーマンスで会場を巻き込み、大きな「輪」が作られました。
会場では「ワンオーガニックマルシェ」も同時開催されており、気軽に始められる「オーガニック」が提案されていました。親に連れられ、マルシェ目的で来場した小学生たちは、最初は性教育に興味のなさそうにしていましたが、次第に美しい音色やスライド、パフォーマンスに目を奪われ、図らずも「いのちの授業」に参加していました。保護者は、「いのちの授業を見よう、と誘っても、絶対に『うん。』とは言わない。こうした場に子どもを連れて来られてよかった。」と話していました。
出演者との打ち合わせを実施

7月6日(土曜日)午後1時30分~5時、陵南福祉センター2階会議室にて、「いのちのつながりフェス」にて行うステージの出演者との打ち合わせが行われました。
打合せでは、メンバー9人に加え、絵本読みパフォーマーのわかさん、歌手の木歌さんが車座となり、第1部・第2部のステージでどのように「いのちの誕生」と「多様性」を表現するかを話し合いました。
木歌さんとわかさんが、「生命の誕生を伝えようと思うと、リアルな性交描写は現実に引き戻されてしまう。精子と卵子の出会いをポエム的に、両親が愛し合うことで生まれてきた、というように芸術的でふんわりと表現できないか。」と問いかけたことに対し、団体メンバーからは「性交だけをタブー視するのではなく、一連の流れを正しく伝えたい思いで活動している。やらしくもなんでもないこと、ぼやかしたり想像に任せることはしたくない。」という意見が出されました。
団体からは、「性交もお産もどちらも生理で、同列に語るのが当たり前の私たちとの壁で、すれ違うことはある意味よくあること。彼女たちのように自然体で生きている方々でも同列に語りにくいイメージだと気付かせてもらいました。そして、だからこそ、私たちが伝えたいことを伝えられるチャンスであるとも思います。」と話がありました。
来場者は年代にも幅があり考え方がさまざまであることから、他の動物と同じように人間も性交によって受精するということを「そうなんだね」と理解してもらうためには、表現を工夫する必要があるとして、両者は「他の動物と人間を同列に並べて表現するのはどうか。」「紙芝居を先に行って、理解を促してからステージに入るのではどうか。」など、伝え方を議論しながらステージ構成を組み立てられていました。
ふれあい夏祭り事業(ふれあいまつり実行委員会)
緑苑ふれあい夏祭り

8月17日(土曜日)午後2時~8時 緑苑中公園で、緑苑ふれあい夏祭りが開催されました。
緑苑地区では少子高齢化が進み、高齢化率が約47%に達し、自治会主催の夏祭りが開催困難となりました。そこで、ふれあいまつり実行委員会が運営を担って、本年も夏祭りを実施しました。ふれあいまつり実行委員会を中心に6団体が協力し、キッチンカー5台が集まり、1団体が出演するなど盛況なイベントになりました。また、「緑苑ふれあい祭りボランティア大募集」という案内に応じた地域ボランティアの皆さん(77人)が祭りを支えました。
午前11時にプレオープンしたキッチンカーには終日多くのお客さんが集まりました。
午後4時に「〇×クイズ」(対象:小学生以下自由参加)がスタートして、参加者(小学生以下)の子どもたちは20問のクイズに大盛り上がりで答えました。正解者はお菓子の景品をもらい大喜びでした。PTAの皆さんが司会進行・出題・会場整備・お菓子の引き換えを行いました。
午後5時からは、かかみがはら炎舞連がよさこい踊りを披露しました。多くの参加者(中学生以下)が炎舞連と一緒に踊りました。一糸乱れぬ踊りに観客は大歓声を送りました。
午後6時から盆踊りとなり、老若男女が各務原音頭や昔からの盆踊り曲を踊りました。子どもたちが知っているアニメソングが流れると一気に踊りの輪が広がり、元気な声が公園に響き渡りました。
午後7時頃に盆踊り演目が終わり踊りの輪が解け、午後8時までは踊りたい人の自由参加となり、午後8時に盛大なふれあい夏祭りが終わりました。
夏祭りに向け打ち合わせを実施

8月4日(日曜日)午後7時~8時30分、緑苑中央集会場ふらっと にて、夏祭りの開催に向けた打ち合わせが行われ、7人が参加しました。
「緑苑ふれあい夏祭り」は、緑苑中公園にて8月17日(土曜日)午後2時~8時に開催予定です。ここまでに、緑苑自治会連合会と打ち合わせを行ったり、ボランティアを募集するなどしながら準備を進めてきました。この日は開催2週間前ということで、チラシの最終校正のほか、購入予定の景品や備品、祭り会場の近隣への挨拶、テントの借用などの進捗状況を確認。また、令和5年度の経験から、当日使用する椅子や机の脚の汚れ対策や、ボランティアに提供するコインの袋詰め、水風船の準備などの役割分担についても話し合われました。
地域の伝統芸能和太鼓の継承と地元愛の育成事業(各務原太鼓保存会)
地域のお祭りで和太鼓を演奏

7月27日(土曜日)・28日(日曜日)に行われた市内各地の夏祭りで、各務原太鼓保存会が、令和5年度事業で制作した「あかりーAKARI―」などの太鼓演奏を披露しました。
7月27日(土曜日)午後6時10分~6時40分は、炉端遺跡公園と岐阜車体工業株式会社の西9・西10駐車場において「三ツ池夏祭り」が開催され、メンバー30名が演奏。ジュニア中級者による「飛燕」チームが西日本大会で披露する予定の「絆」という楽曲や、全国大会での優勝曲である「エンバーク」という楽曲など、オープニング曲も併せて7曲を披露し、会場を沸かせました。また、ステージ後には盆踊りの太鼓や踊りで会場の盛り上げに貢献しました。
会場では、各地の和太鼓団体を紹介する目的で地元「三ツ池やかた保存会」などと情報共有を図り、活動内容の把握に努められました。
7月28日(日曜日)午後7時20分~7時35分、河川環境楽園において開催された「かわしま川まつり」では、川島在住メンバーを中心に応援メンバー10名が演奏を披露。旧川島町で江戸時代から続く伝統行事の「宵やま」で、川島住民が地域のお囃子を奏でながら道行を行い巻きわら船に乗り込む間、演奏が空白となる15分間の演奏を担いました。メンバーの一部は川島住民として道行、巻きわら船での演奏にも参加しており、地域の伝統行事に対する応援の気持ちやつながりを感じさせる場となりました。
おいしく食べていっぱい遊ぼう事業(結愛ポート)
おひさま夏の開放日

8月8日(木曜日)午前9時30分~午後3時 おひさまのおうちで、おひさま夏の開放日を開催しました。
主催者である結愛ポートメンバーと参加者(小学生9人とその保護者)が協力して、環境に優しい廃油石けん作りに挑戦しました。使用する材料には、地域のお店から2週間に1度出てくる「ほうろく菜種油の廃油」が利用されました。廃油に加え、米のとぎ汁やEM発酵液の上澄み、苛性ソーダを使った石鹸作りは、環境保護の意識を高めるとともに、親子で夏休みの楽しい時間を過ごすことができるイベントとして盛況に行われました。
この活動は、結愛ポートのメンバーの指導のもとで行われ、参加者たちは手作り石鹸のプロセスを丁寧に学びました。まず、廃油に苛性ソーダと米のとぎ汁やEM発酵液の上澄みを混ぜ、約30分ほど混ぜ続けると、クリームのような柔らかさになりました。それを牛乳パックに詰める作業が行われました。出来上がったものは約1週間で固まり、さらに1カ月後には石鹸として使用可能になります。
結愛ポートの代表者である各務さんは、子どもたちの自主性を重んじながら進行し、混ぜる過程で液体が発熱する危険性や、混ざった液が強アルカリ性であるため皮膚に付くと危険であることを説明しながら、子どもたちが自主的に作業をする姿を見守りました。各務さんは、「子どもたちが自分の手で作り上げる喜びを感じている様子が良かったです」と今日のイベントを振り返りました。
参加した小学生の女の子は「今日が誕生日なので、誕生日石けんを作ることが出来て良かったです」と、楽しそうに泡だて器で液体をかき混ぜていました。
参加した保護者の一人は、「子どもたちと一緒に環境について考えるよい機会になりました。自分たちが使った油がこんなに役立つ形に生まれ変わるなんて驚きです」と語りました。
参加者の皆さんは、廃油石けん作りを通して、環境への配慮や資源の大切さを実感し、自分たちで作った廃油石けんを大切に持ち帰り、家庭で使用する予定です。
「おひさまのおうち」では、子ども達の自主性を重んじて、子ども達がやりたいことを、自由にできる環境作りを継続していく予定です。
夏野菜とジャガイモの収穫

7月7日(日曜日)午前7時30分~9時30分 蘇原島崎町の畑で夏野菜とジャガイモの収穫が行われました。
5月に植え付けした夏野菜であるナス、トマト、ズッキーニ、バジルやジャガイモなどが収穫期となったため、LINEのオープンチャットで参加者を募っています。
この日は大人5人が参加し、「空心菜は抗酸化作用があって、スムージーなどにも使える。」「バジルは乾燥させてバジル粉にしたり、ジェノベーゼも美味しい。ガパオライスもおすすめ。」など、団体メンバーから使い方のアドバイスを受けながら収穫や草むしりを楽しみました。収穫した野菜は、結愛ポートで調理し子どもたちの「おいしく食べる」活動に活用されます。
参加者は、「無農薬で育てられた野菜は一般的な野菜と比べてトゲの立ち方が違う!」と、今回参加しなかったオープンチャット登録者に向け収穫した野菜の写真を投稿しました。
代表の各務さんは、「今は呼びかけをして集ってもらっているけれど、野菜は日々成長するし、草も生えるので、畑にいつ来てもらってもいい。自主的な動きを目指してゆるやかに活動を促したい。子どもたちは日々成長していて、大人の都合で待たせていたら適切な働きかけができる時期を過ぎてしまう。大人の都合で待ってもらうのではなく、必要とするタイミングで場を提供できるような活動にしていきたい。」と将来を見据えて話しました。
夏野菜植え付け

5月5日(日曜日)午前9時~10時、蘇原島崎町の畑で「夏野菜植え付け」が行われ、14人が参加しました。
夏野菜の植え付けでは、畝を立て、ナス、トマト、ズッキーニ、スイカ、バジルやジャガイモの苗を植え、ヘチマ、オクラ、花オクラなどの種を蒔きました。多くの肥料が必要なもの、牡蠣殻石灰を用いるもの、マルチシートを使うものなど、植物の特性を代表の各務亜紀さんに教わりながら、子どもや保護者、ボランティアスタッフが協力し合って作業を行いました。団体の畑において、肥料には家庭から出た生ごみを微生物の力で分解したものを用いていますが、植え付けと同時に肥料作りも体験させることで、自分が食べたものが野菜の育成に使われる循環を実感できるような工夫もされていました。
また、同日午前11時~午後1時には、蘇原申子町にある団体拠点「おひさまのおうち」でイベントに向けた開放日を設け、参加者同士でたこ焼きを作って食べながら、10月のイベントに向けた相談を始められました。
10月まで、月に1回を目安に開放日を設け、「おいしいものをお腹いっぱい食べる」、「やりたいことをやる」ための、子どもたちの自主的な行動を引き出し、サポートされる予定です。
各務原狂言囃子の会事業(船出の会)
各務原狂言囃子の会を開催

4月27日(土曜日)午後2時~4時、村国座において、船出の会による「各務原狂言囃子の会」が開催されました。来場者およそ180人のうち、初めて狂言に触れる方が全体の1/3を占めました。
船出の会代表の船戸昭弘さんのあいさつの後、演者である三宅近成さんが能楽の成り立ちや、今回公演する「棒縛(ぼうしばり)」「金岡(かなおか)」の2つの演目について内容の解説を行いました。
「棒縛」では、太郎冠者と次郎冠者が盗み飲みをしないように主人に縛られながらもお酒を美味しそうに飲む場面があることから、市内の蔵元・林本店が、歌舞伎役者の名前を冠したお酒「百十郎」の振る舞いで協力し、公演前後や休憩中の来場者同士の会話を盛り上げました。また、「金岡」は、演者も人生で数えるほどしか演じない貴重な演目であることが紹介されました。2つの演目の間には、素囃子「獅子」が演奏され、船戸さんは、解説で獅子が身近な存在であることを伝え、露が落ちる静けさやボタンの花についた露を口にする様子など、音が表現している風景を、観覧者がイメージしやすいようかみ砕いて伝えられました。
40代の男性参加者は、「初めて狂言を観ました。もっと難しいかと思ったけれど、事前に解説があったおかげで思った以上に楽しめたので、また機会があれば観てみたいです。」と話しました。また、事前に鼓体験に参加した女性は、「実際に鼓を触って、いかに難しいかわかっていたので、凄さがより実感できました。」とコメントしました。
小鼓体験を開催

4月6日(土曜日)午後1時~3時、中山道鵜沼宿脇本陣において、船出の会代表の船戸昭弘さんによる小鼓体験が行われ、市内外から16人が参加しました。
最初に、小鼓について説明がありました。体験に使用した小鼓の胴は、およそ50年前、400年前、600年前のものなど。参加者は、「高さや幅はどれも同じだけれど、年代や作者によって彫り方が異なり、音にも差がある。」という船戸さんの説明を聞きながら実物を手に取って眺め、歴史の流れを感じました。
体験では、能楽や狂言で使用する小鼓の持ち方・打ち方の基本をレクチャー。小鼓の音には「チ・タ・プ・ポ」の4種類があること、掛け声を出しながら演奏すること、「ミツジ・ツヅケ・トリ・ノムテ」の4つのパターンがあることなどの説明がありました。
能や狂言の舞台の話では、4月27日(土曜日)の公演について紹介がありました。また、「セリフがある部分では小鼓を打つことはないので、床几をたたみ、横を向いて座ってリラックスしている。出番が近づくと徐に床几を取り出して準備を始める。」などの裏話には、参加者が「知らなかった。」と興味津々で聞き入りました。
川島地区在住の女性は、「先日、鵜沼宿でチラシをみて、絶対に参加したいと思って再訪した。」と話し、今後予定されている川島ライフデザインセンターの小鼓体験講座や村国座で の公演についても興味を示していました。
令和5年度事業取材レポートは以下リンクからご覧いただけます。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課
電話:058-383-1997
まちづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
